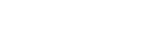診察について
皮膚病全般を診ます。小児でも、アレルギーでも、皮膚に何かあればまずは皮膚科にご相談ください。皮膚の病気は簡単にすると、湿疹、感染症、腫瘍、その他に分けられます。それぞれ放置して良いものかどうかは、見てみないとわかりません。長年あきらめて放置していたものが、実は簡単に治ることや、病気ではないと思っていたものが、実は治療すべき病気であった、ということもあります。恥ずかしくて見せられないものの中には、悪性腫瘍であることもあり、既に手遅れ、ということもあります。いわゆる内臓からくる皮膚病、というのもありますし、後悔先に立たず、ですので、些細なことでも何でもご相談ください。


陥入爪
爪の端が食い込んで痛みのある状態です。
いわゆる深爪で爪が食い込むと、刺さって痛いだけでなく、細菌感染により腫れ上がったり、長引くと肉芽(表皮に覆われていない皮下組織)が盛り上がってきます。
保険診療では、まずは爪を伸ばすことと、抗生剤の内服、外用、液体窒素などを行います。改善しない場合、巻き爪矯正(自費診療)や、最後の手段として、フェノール法(爪の幅を狭くする手術、保険適応)を行います。
エキシマライト
アトピー性皮膚炎、尋常性白斑、乾癬、類乾癬、掌蹠膿疱症、難治性湿疹、円形脱毛症、などの免疫の異常による疾患に有効です。
外用、内服だけでは治らない場合も、併用することで症状を更に抑えることができます。
舌下療法
スギ、ダニアレルギーに対し、完治が期待できる画期的な治療法です。
詳細は舌下療法とはをご参照下さい。
舌下療法の手順
● 適応の確認 (5歳以上)
スギおよびダニのアレルギーに適応があります。採血のクラス2以上で適応になります。
◆ 過去にアレルギー陽性の検査結果がある場合;その結果をお持ち下さい。
◆ 未検査の場合;以下のどちらでも可。
①採血;
正確に数値で結果が出ます。1週間後に結果が出ます。
②指先から数滴血液を採取する簡易法;
イムノキャップラピッド
陰性、陽性の判断ができます。20分で結果が出ます。
● 舌下療法開始
1日目;開始前の準備
抗アレルギー剤と、舌下療法の薬を1日分だけ処方します。
※注; 次回来院日まで内服してはいけません。万が一アレルギー反応が強くて継続できない場合のために、1日分の処方にしています。
◆ 既に抗アレルギー剤を当日朝内服している場合;
薬局で舌下療法の薬を受け取り、当院へお戻りいただき、受付へお声かけ下さい。
以下の「2回目来院日の3.」へ進みます。
2回目来院日;開始日
1. 来院の1時間以上前に、抗アレルギー剤を内服します。
2. 舌下療法の薬をご持参ください。
3. 診察時、医師の指導のもと、舌下療法の薬を舌の下に入れます。
4. 1分間、唾液を飲み込まないで下さい。その後5分間、飲食禁止です。
5. 院内で30分間、アレルギー反応が強く出ないか、確認のため待機して頂きます。
6. 問題なければ、6日間分の舌下療法薬と抗アレルギー剤を処方します。
3回目来院日;定常量へ増量
問題なければ、定常量へ増量します。30日分を処方します。
4回目以降
3~5年、アレルギー反応に注意しながら、毎月(毎回30日分の処方)の受診を継続します。
おおよその処方が切れるまでに、再診してください。
アレルギー検査*中学生から*
アレルギー検査は、疑わしいものを本当に反応するかどうか確認する方法です。したがって、不特定のもの、未知のものから探し出す、ということはできません。疑いのある原因、調べたい項目、またはヒントになるパターンを予めご勘案した上でご来院下さい。
採血
ダニ、ホコリ、花粉などの吸入アレルゲン、ソバ、エビ、カニなどの食物アレルゲンの検査です。結果が出るのに1週間ほどかかります。休診日の前日は、午前中のみ採血を行なっています。
パッチテスト
原因と思われる物質を3mm以下程度の大きさにして持参して頂くか、検査キッドのパッチテストパネルS(ご希望の物質を含む含まないに関わらず、かぶれやすいもの全般のセット(以下項目1+2)。金属はニッケル、クロム、コバルト、金の4種のみ。詳細は パッチテストについて 項目1 項目2 )を使用してみる方法があります。
パッチテストの方法(受診スケジュール)背中または二の腕に貼ります。
第0日目;原因物質を背中に貼る日(注意;シールを剥がすまで濡らしてはいけません。そのため入浴、発汗、プールはできません)
第2日目;シールを剥がす日、1回目の判定
第3または4日目;2回目の判定
第7または8日目;3回目の判定
例;月曜に貼った場合
水曜に剥がして判定、木曜または金曜も受診し判定、月曜に最後に判定し終了。水曜剥がすまで濡らしてはいけません。
*スケジュール上、2日目が固定されるので、金曜開始はできません。
かゆいもの
脂漏性湿疹(頭、顔のかゆみ)、アトピー性皮膚炎、じんましん、手荒れ、水虫、乾燥性湿疹、かぶれ、虫刺され、にきび、汗疱、しもやけ、乾癬、薬のアレルギー、疥癬、トコジラミ(南京虫)、ケロイド、花粉皮膚炎(花粉症)、など。
うつるもの
水いぼ
治療の流れ
①初診時に水いぼの診断をつける。
②痛みの無いようペンレス(麻酔シール)をお渡しします。
③水いぼを取るための予約をする。
④再診の2時間前にペンレスを貼り、診察時シールを剥がし、ピンセットで除去。
※ご兄弟のペンレスが余っていた場合は、初診時に貼付してあれば、その時除去することができます。
その他、水痘(水ぼうそう)、風疹、麻疹(はしか)、リンゴ病、性病、ウイルス性疣贅(いぼ)、帯状疱疹、ヘルペス、など。
感染症に関する、登園、登校、通勤許可書は、保険診察料以外自費分(発行手数料)は頂きません。